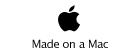研究紹介
生物の進化には,複数の形質が進化して初めて適応的となる場合がしばしばみられます.例えば私が研究している植食性昆虫では,メス親の卵を産む好みと,幼虫が植物を食べて成長できる能力の2つが揃って初めて新たな寄主植物を利用することが可能となります.
ほとんどの昆虫で,メスの好み(産卵選好性)と幼虫の寄主植物への耐性はそれぞれ別の遺伝基盤を持つことが知られています.ということは,寄主転換が起こるには産卵選好性と幼虫の耐性のそれぞれを決めている遺伝子に同じ植物に適応した変異が生じる必要があります.これは一見とても起こりそうには思えませんが,昆虫がその進化の歴史の中で寄主転換を何度も起こしてきたことは間違いありません.よって,寄主転換のような複合的な進化を引き起こすメカニズムがあるはずです.
クルミホソガの実験系を用いて,順遺伝学,逆遺伝学的手法により産卵選好性と幼虫の耐性を司る遺伝子を特定し,複合適応形質をその遺伝基盤から解明するとともに,集団遺伝学,量的遺伝学の手法を用いてその進化プロセスに迫りたいと考えています.

I. 複合適応形質の進化
II. 寄主転換に伴う種分化
III. 鱗翅目ホソガ科の体系学
IV. 植食性昆虫と天敵の相互作用
V. 翅多型の遺伝的背景


新たな環境への適応に伴う種分化の可能性は,古くはダーウィンの種の起原(1859)にまで遡ります.そして,植食性昆虫は生態的な適応に伴う種分化「生態的種分化」の研究材料として注目されてきました.
寄主転換が種分化を促進することは間違いないようですが,まだまだ分かっていないことがたくさんあります.例えば,異なる寄主植物に適応した種内集団は,それぞれの寄主植物へと適応を続けるでしょうが,集団間の遺伝子流入はこの適応を妨げるはずです.よって生態適応と遺伝的分化,そして種分化の関連を調べるには,自然選択と遺伝的浮動,遺伝子流入の効果を包括的に理解する必要があります.
クルミホソガの実験系は,これまでの研究(詳しくは研究業績を参照して下さい)により,遺伝子流入を考える上で不可欠な雑種の適応度や寄主適応力(メス成虫の産卵選好性,幼虫の寄主植物への耐性)の遺伝基盤が分かりつつあります.こうしたクルミホソガ実験系の利点をいかして,寄主転換がどのように遺伝的分化を引き起こし,どのような場合に種分化へと進むのかを解明して行きたいと考えています.
クルミホソガが属しているホソガ科は,そのほとんどの種が幼虫期に植物の主に葉に潜って生活するリーフマイナーです.しかし,その生活様式は実に様々で,一言に潜ると言っても,ライン状に潜るもの,潜りあとが丸く広がるもの,途中から葉の外に出て葉を巻くもの,花びらに潜るもの,実に潜るもの,実の皮や樹皮に潜るものなど,驚くほど多様です.また寄主とする植物も実に多様です.
こうした興味深い生活史や寄主植物の進化系列を解明するには,信頼できるホソガ科の体系を作ることが何よりも重要です.世界中のホソガ研究者と連携し,ホソガ科の高次系統の解明に取り組んでいます.
もちろん,高次系統だけでなく,個々の未記載種の記載や,フィールドでの更なるサンプルの採集,それに伴う生活史形質の収集も同時に行っています.